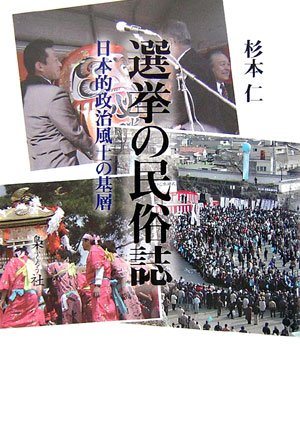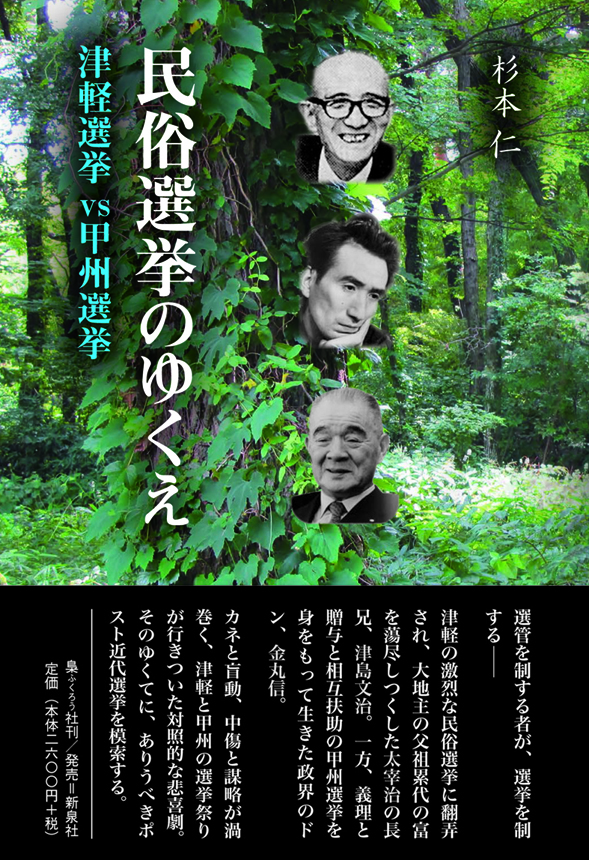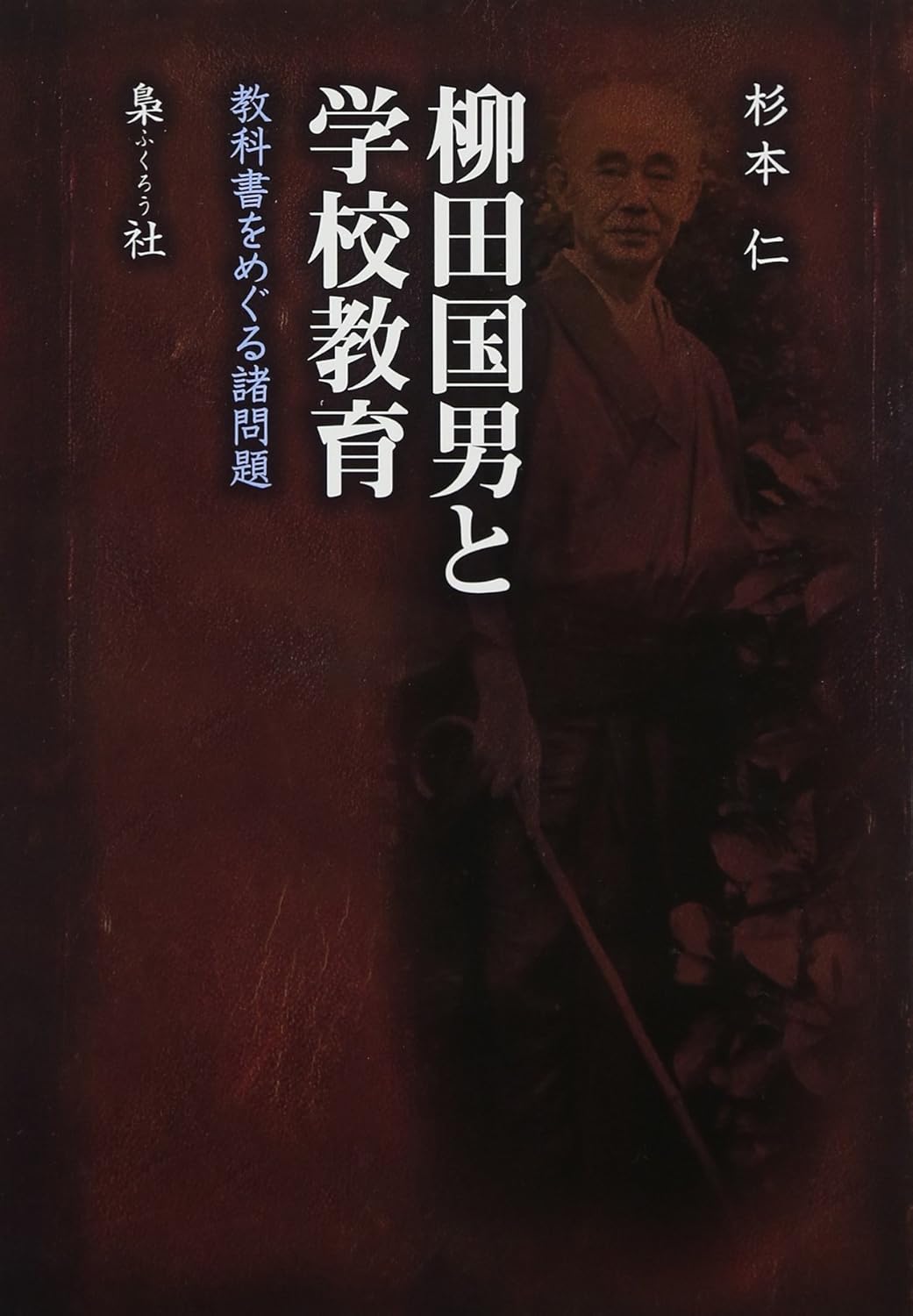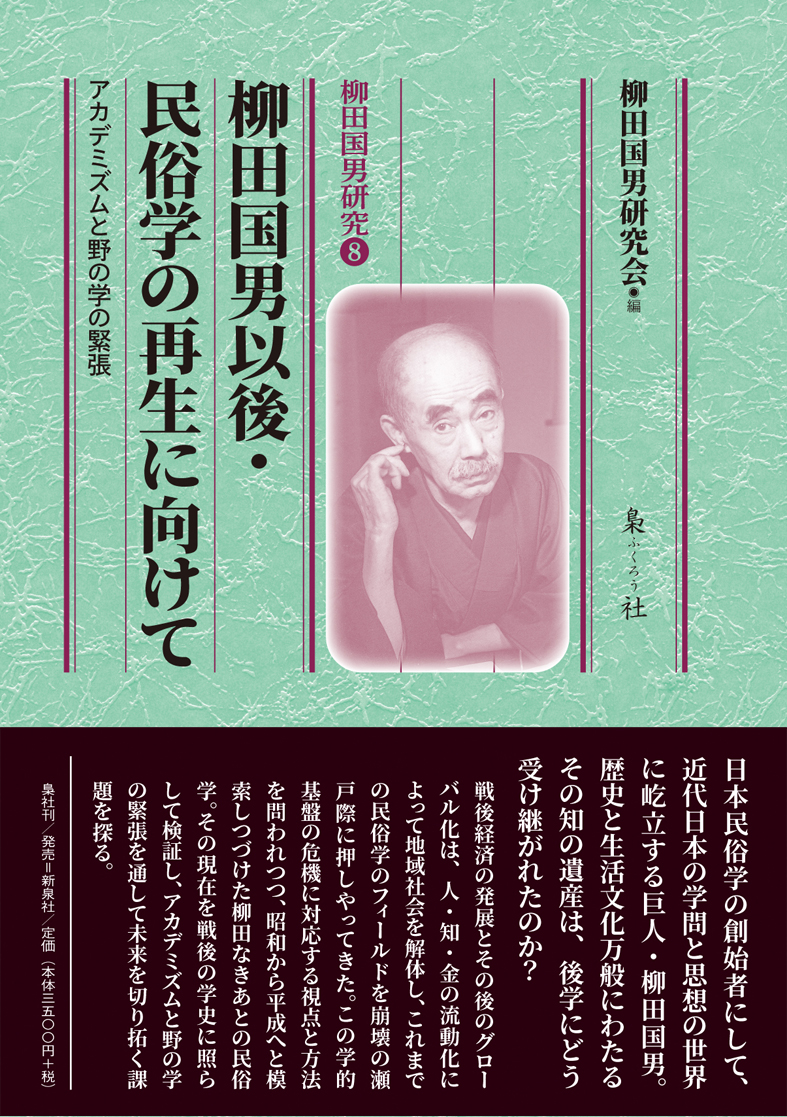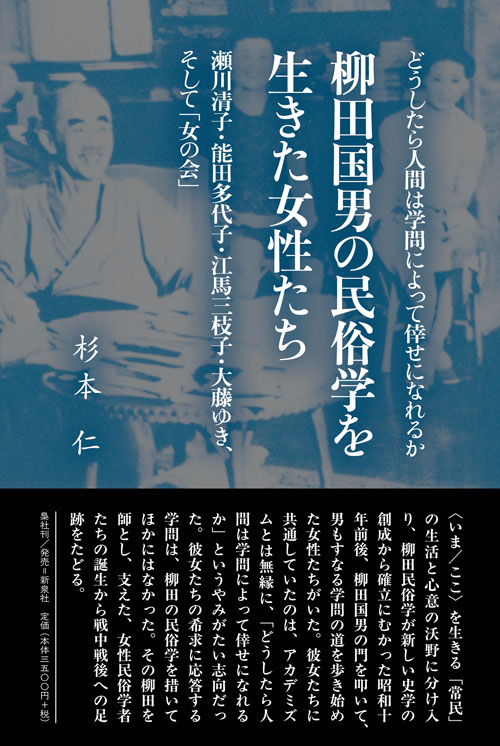
新刊
黎明期の女性民俗学者たちの生と学問の軌跡
柳田国男の民俗学を生きた女性たち
瀬川清子・能田多代子・江馬三枝子・大藤ゆき、そして「女の会」
- 四六判上製
- 352頁
- 3500円+税
- ISBN 978-4-7877-6337-2
- 2025.11.10発行
- [ 在庫あり ]
- 梟社/発行
- 書店サイトへ
書評・紹介
紹介文
〈いま/ここ〉を生きる「常民」の生活と心意の沃野に分け入り、柳田民俗学が新しい史学の創成から確立にむかった昭和十年前後、柳田国男の門を叩いて、男もすなる学問の道を歩き始めた女性たちがいた。彼女たちに共通していたのは、アカデミズムとは無縁に、「どうしたら人間は学問によって倖せになれるか」というやみがたい志向だった。彼女たちの希求に応答する学問は、柳田の民俗学を措いてほかにはなかった。その柳田を師とし、支えた、女性民俗学者たちの誕生から戦中戦後への足跡をたどる。
目次
はじめに
女性による民俗学の出発/ほか
第一章 瀬川清子——「良妻賢母」と闘う自己実現の民俗学
敗戦、そして東北からの再出発/柳田国男の死と「良妻賢母」/ほか
第二章 能田多代子——郷土を凝視する「豆粒拾い」の民俗学
「七ツ前は神」と初物儀礼/席亭の民俗学/ほか
第三章 江馬三枝子——地域を工作する民俗学
プロレタリア運動における江馬修と三枝子/飛驒高山での日常と『飛驒の女たち』/ほか
第四章 大藤ゆき——世を啓蒙する民俗学
恩賜財団母子愛育会/『児やらひ』/ほか
第五章 柳田国男を支えた「女の会」
戦火をくぐりぬけた女性たち/丸山久子——自己抑制と自己主張の民俗学/矢島せい子——ことばをかける民俗学/ほか
おわりに